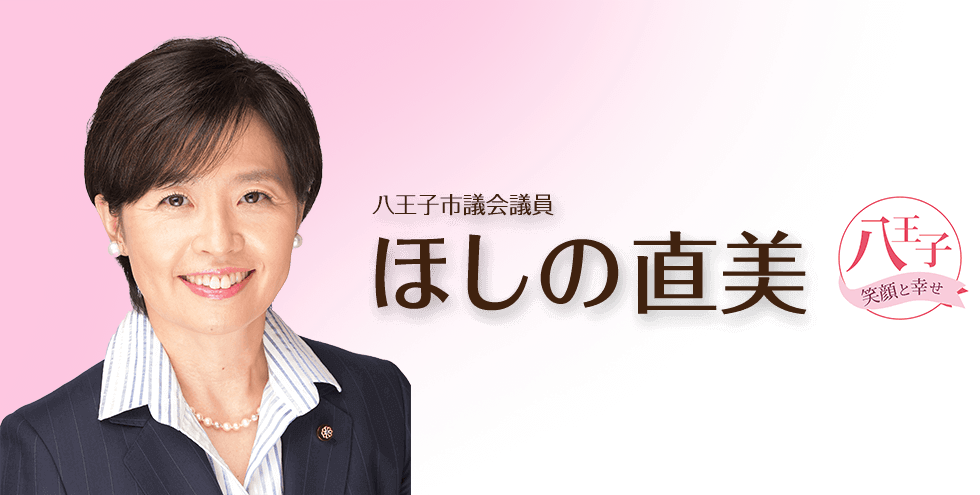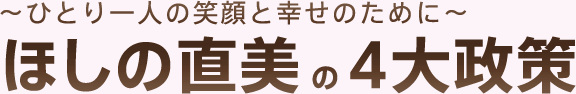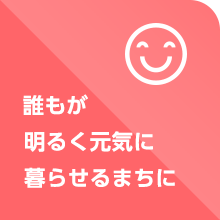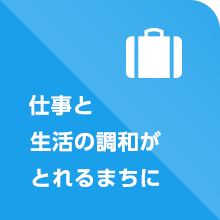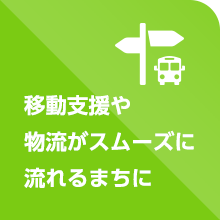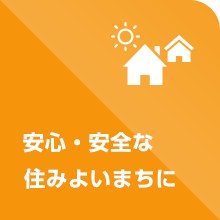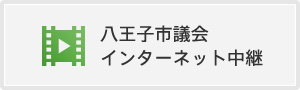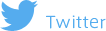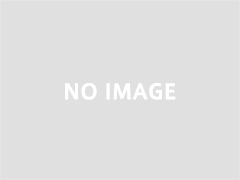 2026年02月19日
2026年02月19日
守れる命を守るために AI細胞診の新時代へ
世界初となる臨床グレードの自律型デジタル細胞診システムが、日本企業・株式会社CYBOと公益財団法人がん研究会有明病院細胞診断部を中心とした研究チームによって開発されました。 従来の2Dスキャンでは捉えきれなかった細胞標本の立体構造を、独自技術「ホールスライド・エッジ・トモグラフィー」により高精細3Dでデジタル化し、AIが自律的に解析します。 この革新的な技術により、細胞診の客観性・精度・効率が大きく向上し、子宮頸がんをはじめとする多くのがんの早期発見に新たな可能性が開かれました。 子宮頸がんは、検診によって前がん病変の段階で発見し、治療できる数少ないがんです。 私はこれまで、検診の大切さを伝える活動を続けてきましたが、今回発表された自律型デジタル細胞診システムは、その未来をさらに前へ進める大きな一歩だと感じています。 専門家不足や判定のばらつきといった現場の課題を、AIとデジタル技術が補い、より多くの人が質の高い検査を受けられる社会へ。 検診を受ける一人ひとりの安心につながるこの技術革新を、私自身の活動とも重ねながら、これからも広く伝えていきたいと思います。 ※本記事は PR TIMES「共同発表:世界初の臨床グレード自律型デジタル細胞診システムを開発」 (2026年2月19日公開)を参考に作成しています。